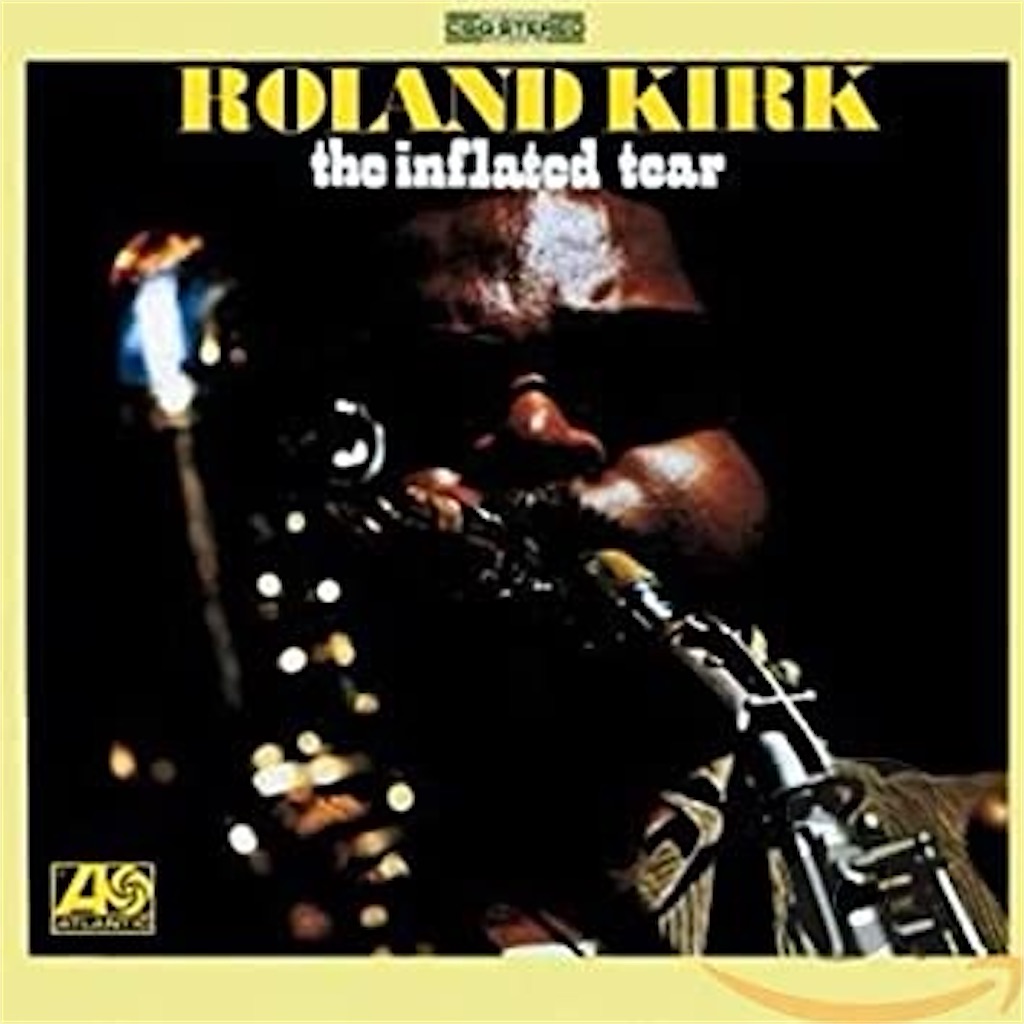エリントンすごいぜ!Vol.13
〜エリントンとヴォーカル序論〜
1.アイヴィー・アンダーソン~忘れられたジャズシンガー~
1)It Don't Mean A Thing(If It Ain't Got That Swing)(Ellington, Mills)
Arthur Whetsel, Cootie Williams, Freddie Jenkins(tp),
Joe”Tricky Sam” Nanton,(tb), Lawrence Brown, Juan Tizol(btb), Johnny Hodges(ss,as,cl), Barney Bigard(cl,ts), Harry Carney(bs,cl,as), Ellington(p), Fred Guy(banjo), Wellman Braud(b),
Sonny Greer(drms), Ivie Anderson(vo)
Recorded at New York in February 2, 1932
2)All God’s Chillun Got Rhythm(Gus Kahn, Walter Jurmann, Bronislaw Kaper)
Wallace Jones, Cootie Williams(tp), Rex Stewart(cor),
Lawrence Brown, Joe”Tricky Sam” Nanton(tb), Juan Tizol(btb), Johnny Hodges(ss,as), Otto Hardwick(as, cl), Barney Bigard(cl,ts), Harry Carney(bs,cl),
Ellington(p), Fred Guy(g), Bill Taylor(b), Sonny Greer(drms),
Ivie Anderson(vo)
Recorded at New York in June 8, 1937
3)I’m Checkin’Out Goom-Bye (Ellington)
Wallace Jones, Cootie Williams(tp), Rex Stewart(cor),
Lawrence Brown, Joe”Tricky Sam” Nanton(tb), Juan Tizol(btb), Johnny Hodges(ss,as), Otto Hardwick(as, cl), Barney Bigard(cl,ts), Harry Carney(bs,cl),
Ellington(p), Fred Guy(g), Bill Taylor(b), Sonny Greer(drms),
Ivie Anderson(vo)
Recorded at New York in June 12, 1939
4)Chocorate Shake(Paul Francis Webster, Ellington)
Wallace Jones, Cootie Williams(tp), Rex Stewart(cor),
Lawrence Brown, Joe”Tricky Sam” Nanton(tb), Juan Tizol(btb), Johnny Hodges(ss,as), Otto Hardwick(as, cl), Barney Bigard(cl,ts), Harry Carney(bs,cl), Ellington(p), Fred Guy(g), Bill Taylor(b),
Sonny Greer(drms), Ivie Anderson(vo)
Recorded at Hollywood, in June 26, 1941
5)I Got It Bad(And That Ain’t Good)(Paul Francis Webster, Ellington)
Wallace Jones, Cootie Williams(tp), Rex Stewart(cor),
Lawrence Brown, Joe”Tricky Sam” Nanton(tb), Juan Tizol(btb), Johnny Hodges(ss,as), Otto Hardwick(as, cl), Barney Bigard(cl,ts), Harry Carney(bs,cl),
Ellington(p), Billy Strayhorn(celesta), Fred Guy(g), Bill Taylor(b), Sonny Greer(drms), Ivie Anderson(vo)
Recorded at Hollywood, in June 26, 1941
3.ジャズヴォーカルとエリントン
6)It Don't Mean A Thing(If It Ain't Got That Swing)(Ellington, Mills)
Rosemary Clooney(vo),
Clark Terry(tp,frh), Cat Anderson, Willie Cook, Ray Nance(tp), Gordon Jackson, Britt Woodman(tb), John Sanders(btb), Johnny Hodges(as), Russsell Procope(as, cl), Paul Gonsalves(ts), Jimmy Hamilton(cl,ts), Harry Carney(bs,bcl, cl), Ellington(p), Jimmy Woode(b), Sam Woodyard(drms)
Recorded at Columbia 30th street Studios, Manhattan, New York on January 23 & 27, 1956(Ellington)
Recorded at CBS Studios, Los Angeles under the direction of Billie Strayhorn, on February 8 & 11, 1956(Clooney)
7)Day Dream(John Latouche, Strayhorn)
Jo Staford(vo), Johnny Mandel(arr, cond),
Ray Nance, Fagerquist, Conte Candoli(tp), Lawrence Brown(tb), Johnny Hodges(as), Ben Webster(ts), Harry Carney(bs),
Jimmy Rowles(p), Russ Freeman(celesta), Bob Gibbons(g),
Joe Mondragon(b), Mel Lewis(drms)
Recorded at Columbia 30th street Studios, Manhattan, New York
on July 15, 1960
8)All I Need Is Girl( Stephen Sondheim, Jule Styne)
Frank Sinatra(vo), Billy May(arr,cond),
Cootie Williams, Cat Anderson(tp), Lawrence Brown(tb),
Johnny Hodges(as), Russell Procope(as, cl), Paul Gonsalves(ts), Jimmy Hamilton(ts,cl), Harry Carney(bs),
Ellington(p), Jeff Castleman(b), Sam Woodyard(drms) etc.
Recorded in Hollywood, Los Angeles December 11-12, 1967
9)Caravan(Juan Tizol, Ellington, Mills)
Ella Fitzgerald(vo), Clark Terry(tp,frh), Cat Anderson, Willie Cook, Shorty Baker or Ray Nance(tp), Quentin Jackson, Britt Woodman, John Sanders(btb), Johnny Hodges(as), Russsell Procope(as, cl), Paul Gonsalves(ts), Jimmy Hamilton(cl,ts), Harry Carney(bs,bcl, cl), Ellington(p), Jimmy Woode(b), Sam Woodyard(drms)
Recorded in New York, June 27, 1957
3.エリントンにおけるゴスペルミュージックの追求
10)part 4(a.k.a. Come Sunday)(Ellington)
Mahalia Jackson(vo), Cat Anderson, Harold Baker(tp),
Ray Nance(tp,vln),
Clark Terry(tp,frh)?
Quentin Jackson, Britt Woodman, John Sanders(btb), Johnny Hodges(as), Russsell Procope(as, cl), Paul Gonsalves(ts), Jimmy Hamilton(cl,ts), Harry Carney(bs,bcl, cl), Ellington(p), Jimmy Woode(b), Sam Woodyard(drms)
Recorded at Columbia 30th street Studios, Manhattan, New York in February 11, 1958
11)Come Sunday(Ellington)
Eric Dolphy(bcl), Richard Davis(b)
Recorded at Music Maker’s Studios, New York, on July 1 & 3, 1963
12)David Danced Before The Lord(Ellington)
Jon Hendricks(vo),
Cat Anderson, Cootie Williams, Herbie Jones, Mercer Ellington(tp), Lawrence Brown, Buster Cooper(tb), Chuck Conners(btb),
Johnny Hobges(as), Russell Procope(as,cl), Paul Gonsalves(ts), Jimmy Hamilton(cl,ts), Harry Carney(bs,bcl,cl),
Ellington(p), John Lamb(b), Louis Bellson(drms),
Bunny Briggs(tap dancing),
Choir; Herman McCoy Choir
Recorded at Grace Cathedral, San Francisco, on September 16, 1965(Live Broad Casting Recordeing ?)
4.エンディング
13)It’s Freedom(Ellington)
Alice Babs, Devonne Garder, Trish Turner, Roscoe Gil(vo),
Cat Anderson, Cootie, Williams, Herbie Jones, Mercer Ellington, Money Johnson(tp),
Lawrence Brown, Buster Cooper, Benny Green(tb),
Chuck Conners(btb)
Johnny Hodges(as), Russsell Procope(as),
Paul Gonsalves(ts), Jimmy Hamilton(cl,ts),
Harry Carney(bs,bcl, cl),
Ellington(el-p, narration), Jeff Castleman(b),
Sam Woodyard, Steve Little(drms),
Choirs;
The AME Mother Zion Church Choir, Choirs of Hilda’s and St. Hugh’s School, Central Connecticut State College Singers,
The Frank Parker Singes
Recorded at Fine Studios, New York, on January 22 & February 19